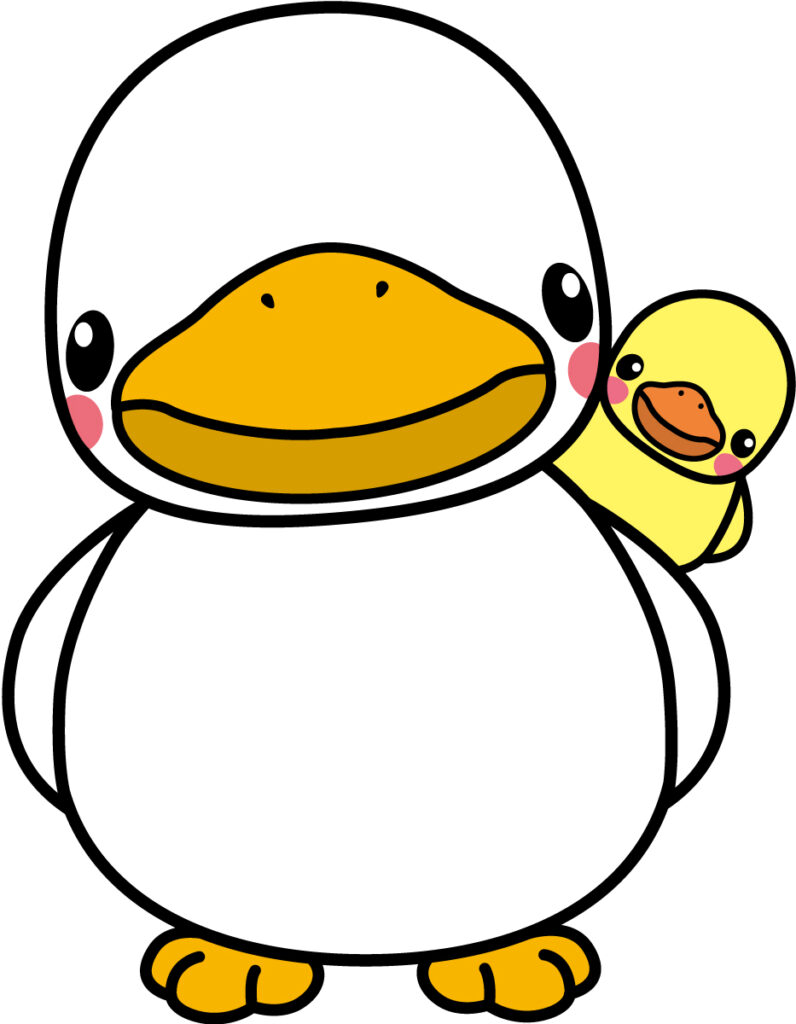元旦の「令和6年能登半島地震」以降、所有物件の“耐震性”について気になっている方も多いのではないでしょうか。地震に強い建物とはどういうものなのか、法的な基準や構造についての基礎知識をご紹介します。
新・旧に続く3つ目の2000年基準
建物の耐震性能については、「旧耐震」「新耐震」という区分けがよく知られています。しかし、耐震基準にまつわる法律は数年おきに改正されており、現在は新・旧の基準だけでなく、その後に登場した「2000年基準」についても重要視されています。
【旧耐震基準】
1950年の建築基準法制定によって示された耐震基準です。震度5程度の地震では倒壊しないことが前提となっている一方、震度6以上の大地震に耐えられるほどの耐久力は規定されていません。
【新耐震基準】
1981年の建築基準法の大改正に伴って示された耐震基準です。1978年に発生した宮城県沖地震を機に旧基準が大幅に見直され、震度6~7の地震でも倒壊しない構造とするための規定が設けられました。具体的には、一次設計・二次設計の二段階で耐震性のチェックがされるようになりました。
【2000年基準】
1995年の阪神・淡路大震災では、震度7の揺れに耐えられず大量の木造住宅が倒壊しました。これを受けて定められたのが、2000年の建築基準法改正に伴う「2000年基準」です。この新基準では、地盤調査や構造計算、使用部品、耐力壁の配置などにも新ルールが加えられ、特に木造住宅の耐震性強化が図られました。
ちなみに、2000年基準の耐震性能が図らずも示されたのが、2016年に発生した熊本地震です。国土交通省の発表によれば、最も被害の大きかった熊本県益城町において、旧耐震基準の木造住宅の28. 2%、新耐震基準の木造住宅の8.7%が倒壊に至った一方で、2000年基準の木造住宅の倒壊率は2.2%。築年数による差もあるとはいえ、新基準が被害の拡大を食い止めたといえそうです。
倒壊を防ぐポイントは「基礎」「壁」「接合部」
地震で強い建物をつくるには、主に「基礎」「壁」「接合部」がポイントといわれます。2000年基準もこの3点に対して具体的な施工ルールが定められており、基礎に関しては地盤に合わせた最適な形状とすること、それに伴い、地盤が建物の重みにどれだけ耐えられるかを示す地耐力(ちたい・りょく)を調べる地盤調査が必須となりました。
壁については偏心率という指標が定められ、耐力壁をバランスよく配置することが規定されました。これは2000年以前の基準下において、窓が多い南側に壁が少なく、北側に耐力壁が偏るような構造の建物が多く建築されたためで、実際にこのような建物が捻れるように倒壊するケースが阪神・淡路大震災では多く見られました。
接合部に用いる接合金物についても細かな規定ができました。柱や梁、壁など主要構造部の継ぎ目に正しく金物を使用することで、建物の構造を強固にし、柱が土台から抜けてしまう「ほぞ抜け」を防ぎます。
建物ではなく命を守るための耐震基準
さらに2025年には、新たな建築基準法の改正が迫っています。これは増加する「ZEH」等の省エネ住宅に対応するもので、断熱材の増加や高断熱窓サッシの採用、屋根へのソーラーパネル設置など、増加傾向にある住宅重量およびその負荷に耐えうる壁量・安全性の確保を目指しています。今後も耐震性能に関する規定は増え、建物の性能は向上していくでしょう。
ただし耐震基準とは、あくまで「人の命が建物の即座の崩落・倒壊で奪われない」ための、最低限の基準でしかありません。たとえ2000年基準の建物であっても、建物が損壊し住めなくなる可能性がある限り、避難場所の事前案内や防災工具の用意、地震保険の加入など、“その先”を見据えた対策もご検討ください。